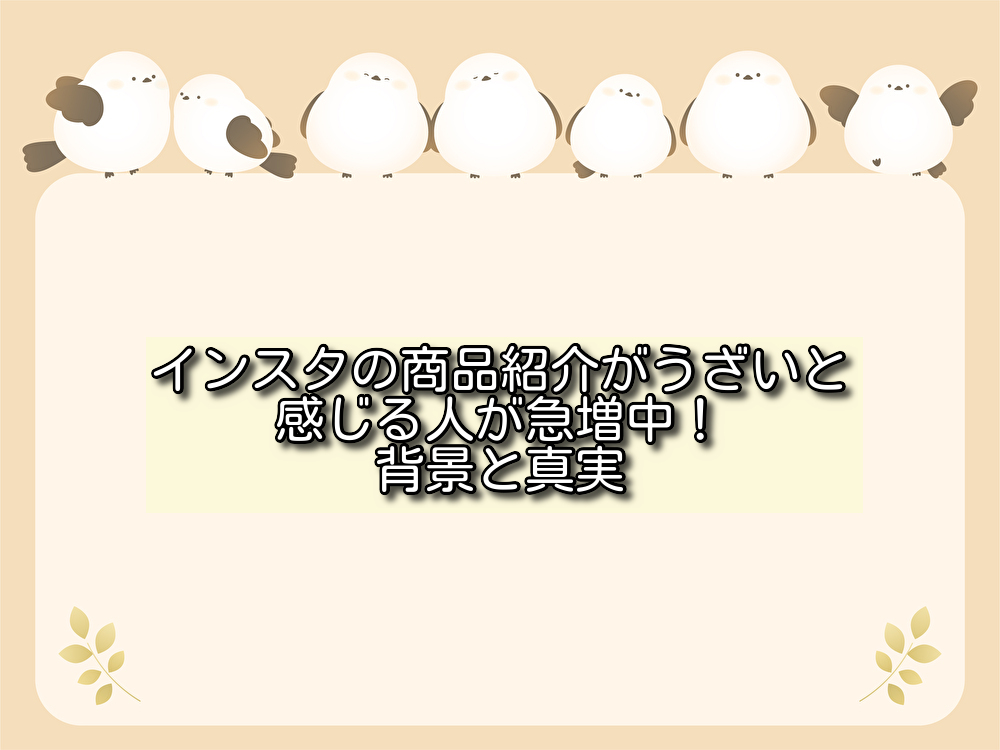SNS、とくにInstagramやTwitterでは、最近「prばかり」「ステマだらけ」と感じるユーザーが急増しています。魅力的なグラマーの投稿が実はPR案件だったり、自作自演のレビューや胡散臭い商品紹介が目立つようになり、「から買いたくない」「見るだけ」という消費者も少なくありません。
とくに楽天ルームやアフィリエイト経由の収入報告が話題になる一方で、「気持ち悪い」「違法じゃないの?」「見方が知りたい」という声も多くなっています。この記事では、インフルエンサーのPR投稿に対する世間の本音やステマの問題点、そして今後の法律や規制の動きについて詳しく解説します。
この記事でわかること
- PR投稿やステマが嫌われる背景とその理由
- インフルエンサーがもらっている報酬の相場と仕組み
- ステマと合法なPRの違いと見分け方
- 今後のステマ対策や法律による規制の方向性
インスタの商品紹介がうざいと感じる理由とは?
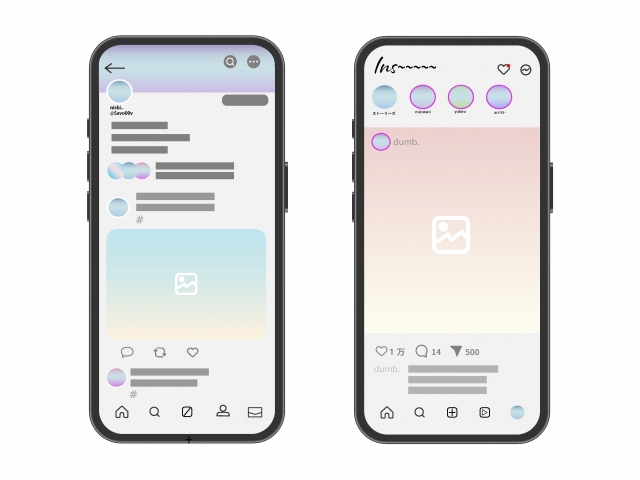
SNSの普及とともに、インスタグラムをはじめとしたプラットフォーム上では、企業とタイアップした投稿が急増しています。一見おしゃれで自然な投稿も、実はPR案件であることが多く、ユーザーは知らず知らずのうちに広告を見せられているのです。この章では、多くの人が「うざい」「ステマっぽい」と感じるようになった背景を、具体的な投稿内容やPRの手法に着目して解説していきます。
PRばかりの投稿が目につくようになった
最近のInstagramでは、PR(広告)投稿がタイムラインを埋め尽くすようになってきました。以前は友人の何気ない日常や、気になるインフルエンサーのリアルな発信が中心だったのに、気づけば企業案件やタイアップばかり…。これが「うざい」と感じる大きな原因になっています。
とくにストーリーズやリールなど、視聴率の高い機能にPRを差し込む手法が一般化し、ユーザーは広告と日常の区別がつきにくくなっています。それにより、「またこれか…」といううんざり感を抱くようになるのです。
一方で、発信者側にとってPRは貴重な収入源でもあります。そのため案件を断るわけにもいかず、同じような商品を繰り返し紹介する状況が生まれています。これが“PRばかり”の印象をさらに強めているのです。
投稿者とフォロワーとの間に「広告疲れ」が広がる今、PR投稿の頻度や見せ方には一層の工夫が求められる時代になっています。
ステマだらけで信頼できない情報が増加
インスタグラム上で「ステマ(ステルスマーケティング)」が蔓延していることも、多くの人が商品紹介をうざいと感じる理由のひとつです。表向きは“個人のおすすめ”として紹介されているのに、実は報酬をもらっていたり、PRであることを隠していたり…。このような投稿は、ユーザーの信頼を大きく損ないます。
とくに厄介なのは、投稿文に「PR」や「タイアップ」などの表記が一切ないケースです。これは景品表示法にも抵触する可能性がある違法な行為ですが、現実には見逃されている場合も多く、フォロワーの中には「また嘘かも」と疑う気持ちが強まっているのが実情です。
さらに、フォロワー数の少ない一般人風アカウントによる“仕込み”レビューも横行しており、「本当の口コミがどれなのか分からない」という不安感を抱く人が増えています。
ステマが当たり前になってしまったこの環境では、誠実な投稿すら疑われがちです。その結果、「どうせ裏で金もらってるんでしょ」と冷めた目で見られるようになり、投稿者とフォロワーの間に深い溝ができてしまっています。
自作自演や嘘っぽいレビューに不信感
Instagramでよく見かけるのが、「これ本当に使ってるの?」と疑いたくなるようなレビュー投稿です。まるで企業の宣伝文句をそのまま写したかのような表現や、過剰に美化された写真が並ぶと、自作自演のように感じられてしまいます。
中には、商品を開封する場面もなく、実際の使用感も語られていない投稿もあります。そうした内容を見て「絶対使ってないでしょ」と感じるユーザーは少なくありません。
本来、SNSの魅力は“リアルさ”にあります。だからこそ、あまりに作られた感のあるレビューは逆効果。信頼を得るどころか、「嘘くさい」と一気に不信感を抱かれてしまいます。
フォロワーとの信頼関係を築くには、リアルな感想や正直なレビューが必要不可欠です。ですが、報酬や案件に気を取られ、自作自演的な投稿が増えることで、「もう信用できない」という声が広がっているのが現状です。
報酬目当てのPR案件が多すぎて引く
Instagramでは、商品の紹介をすることで報酬が得られる仕組みが一般的になっています。そのため、「これ本当におすすめなの?」「ただお金が欲しいだけじゃないの?」と感じさせる投稿が増加しています。
特にフォロワー数の多いインフルエンサーにとって、PR案件は大きな収入源です。結果として、似たような投稿が連続したり、興味もなさそうな商品まで紹介していたりと、“報酬目当て感”が前面に出てしまうのです。
そのような状況が続くと、フォロワーは「この人、もう信用できないな」と感じてしまいます。とくに同じような美容アイテムや健康食品が頻繁に登場すると、「本当に全部使ってるの?」という疑問が拭えません。
さらに、収益化のために“毎日がPR投稿”というようなアカウントも増え、インスタ全体が広告で溢れているような印象を与えてしまっています。その結果、情報の質が薄まり、「また広告か…」とスクロールを止めずに流す人が増えているのです。
楽天ルームやアフィリエイトリンクの氾濫
近年、インスタグラム上で楽天ルームやアフィリエイトリンクを使った投稿が急増しています。フォロワーにとっては、日常の投稿を見にきたはずなのに、気がつけば「○○はこちらから購入できます」といったリンクだらけの投稿が並び、「広告目的ばっかり」とうんざりすることも。
特に楽天ルームは、手軽に報酬が得られる仕組みであるがゆえに、多くのユーザーが参入し、似たような投稿がタイムラインを埋め尽くしています。商品を紹介する目的ではなく、「とにかくリンクを踏ませたい」という意図が透けて見えると、見る側としては嫌悪感が募ります。
しかも、投稿者自身が使っていない商品や、過剰に美化した商品説明が添えられていることも多く、「これは本当におすすめしてるの?」と疑念を抱く原因に。
楽天ルームやアフィリエイトは、上手に使えば便利な情報源になり得ますが、押しつけがましくなった瞬間、フォロワーの信頼は一気に崩れてしまいます。
インスタの商品紹介がうざい|この時代に知っておくべきこと

インスタグラムでのPR投稿に違和感を持つ人が増えている背景には、単なる「うざい」という感情だけでなく、時代の変化とユーザーの意識の変化が影響しています。
この章では、現代のSNSユーザーがPRやステマ投稿にどう向き合っているのか、そして法律や規制の観点からどのような動きがあるのかについて、より深く掘り下げていきます。
見るだけ・経由しないフォロワーの変化
かつては、インスタグラマーの紹介をきっかけに商品を購入する人も多くいました。しかし最近では、「紹介されても買わない」「リンクは踏まず、見るだけ」というスタンスに切り替えるフォロワーが急増しています。
その理由は明確です。「またPRか…」と感じさせるような投稿が増えすぎたことで、ユーザー側に広告への耐性や警戒心が生まれているのです。結果として、紹介されても「どうせ報酬目的でしょ?」というフィルターを通して見られるようになっています。
さらに、「経由すると投稿者に報酬が入る」と知っているフォロワーは、あえて別経路で検索したり、楽天やAmazonで直接商品名を入力して購入するケースも増えています。これは、ステマや過剰な広告に対する“ささやかな抵抗”とも言えるでしょう。
「参考にはするけど、信用はしてない」——このような態度の変化は、インスタで商品紹介をする側にとっては非常に大きな課題です。フォロワーの“見る目”が確実にシビアになってきているのです。
ステマとは何か?Instagramでの線引き
「ステマ」とは“ステルスマーケティング”の略で、広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する手法のことを指します。Instagramではこのステマが問題視されることが多く、ユーザーの不信感を生む大きな要因になっています。
本来、PRやタイアップ投稿には「#PR」「#広告」などの明記が必要です。しかし、それを小さく表示したり、文末にこっそり記載したり、あるいはまったく明示しない投稿も珍しくありません。これでは、フォロワーは「本当にその商品が好きなのか、それとも報酬目的なのか」が分からず、騙されたような気持ちになります。
さらに、インスタでは日常の延長線のような自然な投稿が好まれるため、宣伝と気づかせない形でのアピールが通りやすい環境が整っています。こうした背景が、ステマの温床となっているのです。
消費者庁などもガイドラインを整備し、ステマの明示義務を強める動きを見せていますが、実際の運用にはまだまだグレーな部分が多く、フォロワー側の不信感は解消されていません。Instagramを使った発信には、正直さと透明性がより一層求められる時代になっています。
タイアップ投稿が嫌われる背景と本音
タイアップ投稿とは、企業とインフルエンサーなどの投稿者が協力して行う広告投稿のことです。Instagramでは一般的な手法ですが、これが「うざい」と言われる最大の原因にもなっています。
その理由は、タイアップ投稿が“宣伝っぽさ”を隠せていないケースが多いからです。見せ方や言葉遣いに工夫が足りないと、フォロワーは「これ、広告でしょ」と一瞬で見抜きます。そうすると、投稿全体が魅力的に映らず、「興味がない」「またか」とネガティブな印象を与えてしまうのです。
また、投稿頻度が高いと、いかに内容がよくても「お金のために投稿している」という印象が先行してしまい、本音が伝わらなくなります。ユーザーとしては、「この人が本当にいいと思っているのか、それとも企業に言わされているのか」が分からなくなってしまうのです。
フォロワーの共感や信頼を得るには、タイアップだからこそ“本気でおすすめしたい理由”や“自分の言葉”が不可欠です。ただ報酬のために紹介しているだけのように見えてしまうと、共感はおろか、嫌悪感すら生まれてしまいます。
インフルエンサーと一般人の投稿の違い
Instagram上では、同じように見える商品紹介でも、「インフルエンサー」と「一般人」の投稿には大きな違いがあります。この差を感じ取ったフォロワーが、「うざい」と感じる要因にもなっています。
インフルエンサーは影響力があるため、企業とのタイアップやPR案件が多く、投稿にも洗練されたビジュアルや文章が使われます。一方、一般人の投稿はより素朴でリアルな内容が多く、「実際に使ってみた感想」が伝わることが多いです。
この違いがあることで、フォロワーは「どちらを信用すべきか」と戸惑う場面が増えています。とくに、インフルエンサーの投稿は見た目がキレイすぎるあまり、「本音が見えない」「企業の代弁者にしか見えない」といった印象を与えてしまうことも。
また、最近ではフォロワー数の少ない“マイクロインフルエンサー”でもPR案件を受けられる時代になったため、「一般人のフリをした宣伝」も増えています。これにより、どの投稿が本当に信頼できるのか分からなくなり、情報の価値が下がってしまっているのです。
規制や法律、今後のステマ対策の動き
Instagramに限らず、SNSにおけるステルスマーケティングへの批判が高まる中、各国で規制の動きが強まっています。日本でも2023年には消費者庁が「広告であることを明示しない投稿は違法」と明言し、ガイドラインの整備が進められました。
具体的には、「#PR」「#広告」などの明記がなければ、企業にも投稿者にも法的責任が及ぶ可能性があります。また、違反が悪質な場合は、景品表示法に基づく措置命令や課徴金の対象にもなる恐れがあります。
こうした背景から、企業側も慎重な姿勢を取るようになり、インフルエンサーに対して明確な表示ルールを求めるケースが増えてきました。投稿者側も、今までのような“曖昧なPR”では通用しない時代に突入しています。
ただ、規制が進んでいるとはいえ、現場レベルではまだグレーな投稿が多いのも事実です。利用者自身が正しい情報を見極めるリテラシーを持つことも、これからのInstagram活用において重要なポイントになっていくでしょう。
まとめ

この記事のポイントをまとめます。
- SNSでは「PRばかり」「ステマだらけ」と感じる投稿が増えている
- 自作自演や嘘っぽいレビューが信頼を失わせている
- 報酬目当てのPR案件が乱立し、消費者が冷めている
- 楽天ルームやアフィリエイトのリンクに嫌悪感を持つ人も多い
- 「見るだけ」「経由しない」ユーザーの行動が広がっている
- ステマの線引きが曖昧で、消費者の混乱を招いている
- インフルエンサーと一般人の投稿に温度差がある
- 法律や規制の整備が進み、企業側にも変化が求められている
- ユーザーはPR表記や広告であることの明示を重視している
- 今後は信頼性や透明性が評価される時代になっていく
SNSにおけるPR投稿やステマの問題は、単に「嫌い」「うざい」といった感情にとどまらず、情報の信頼性や消費者保護という観点でも大きな課題となっています。今後、企業やインフルエンサーに求められるのは、透明性を持った発信とユーザーとの誠実なコミュニケーションです。見る側も、正しい知識を持って投稿を判断していくことが重要になってくるでしょう。